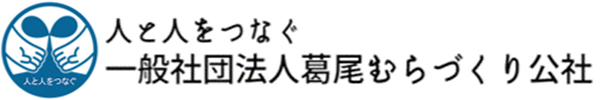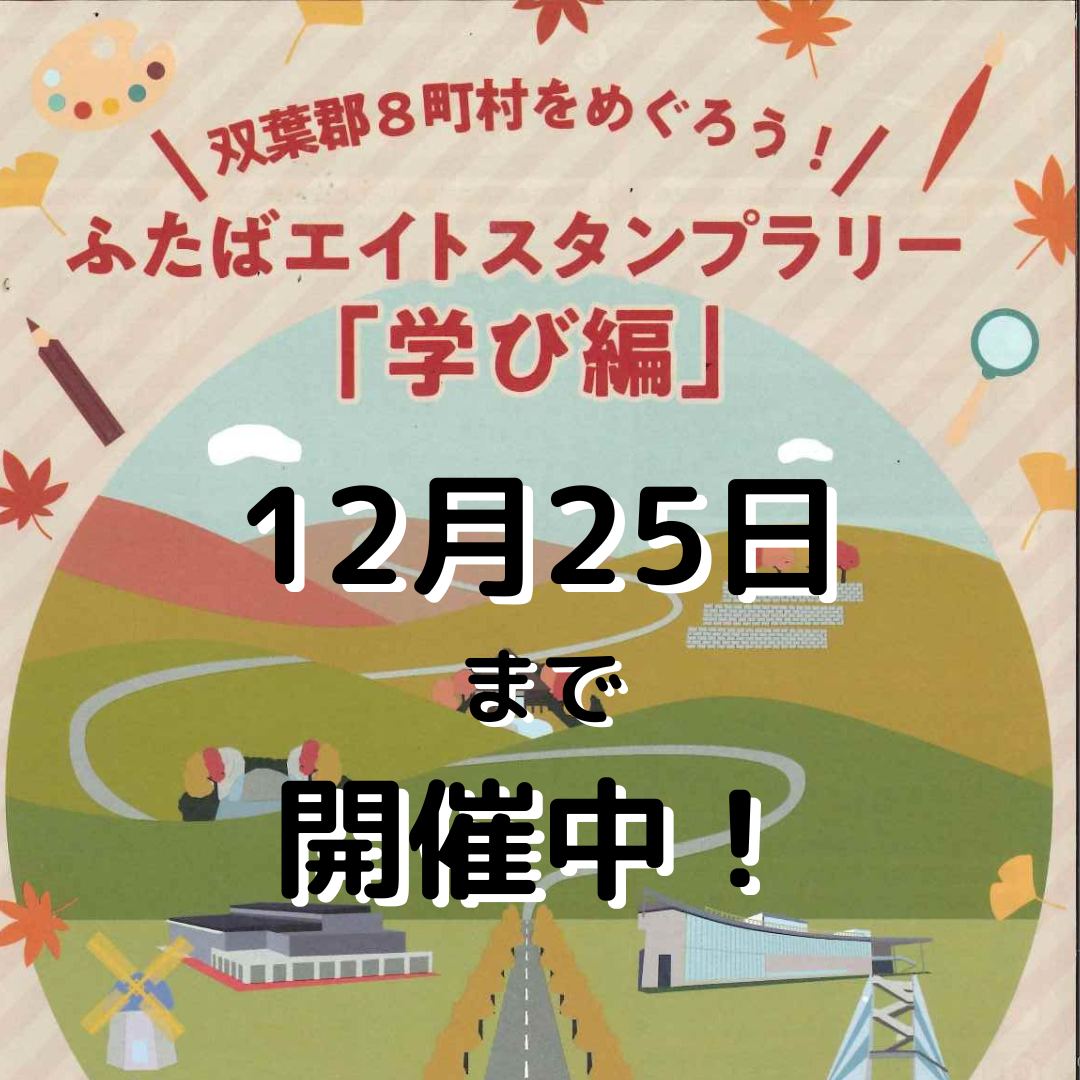葛尾コラム:今に受け継がれる葛尾大尽物語
葛尾村に伝わる葛尾大尽のストーリーは、今から400年前の戦国時代に遡ります。
戦国時代の武将、村上義清の居城「葛尾城」をめぐって武田信玄と激闘が繰り広げられ、義清は惜しくも敗れました。その際、義清の家来だった松本勘解由介が相馬に落ち延び、相馬当主から三春領と相馬領の国境警備を頼まれて住み着いたこの地を「葛尾」と名付けたといわれています。こちらのサイトに葛尾大尽について記載されています。
そんな葛尾大尽の伝説を後世に受け継ぐため、2008年に結成した「葛尾村再発見プロジェクト」によって葛尾大尽物語の人形劇は始まりました。
途中、東日本大震災やコロナ禍により中断した時期もありましたが、今でも年に数回「葛尾村再発見プロジェクト」から名前を変えた「元気なかつらおプロジェクト」によって、この葛尾大尽物語は上演されています。
このページでは、葛尾大尽物語のストーリーを対話形式で紹介します。
皆さんも人形劇の上演があったら、是非見に来てください。
葛尾大尽物語(人形劇)
第1章「葛尾大尽の祖先、勘解由介の頃」
(闇の中「葛尾大尽荒屋敷」の吟詠が流れ、落城の風景)
(一転して、緑豊かな里山の風景)
(一羽のキジが舞い降りる、客席に向かって)

『私(わたくし)、奥州阿武隈の地に住むキジでございます。三春・相馬両藩に治められておりましたこの地に、天正の頃、一人の武士がやって参りました。身はやつれておりますが、眼光鋭く、由緒正しい家柄の出とおぼしき、品位を持つ若者なのでありました。』
(下手に退場)
(上手より、勘解由介、杖をつきつつ登場)

『信州葛尾の地を追われ、故郷を遠く離れて来たけれど、ここは一体、どこなのだろう。緑豊かなこの地、光は輝くけれど私の心は、なんと寂しい。武田勢との戦いに勝ちさえすれば、私には洋々たる未来が待っていたのだ。父上は、母上は、どうなったのだろう。ああ、こうして奥州の山中をさまようことが、私の運命(さだめ)と言うのか・・・。あてもなくさすらい、やがて朽ち果てることが私の運命と言うのか・・・。ならば、神を、仏を呪いたい。』
(勘解由介、くずれて地にひれ伏す)
(おみつ、手に持つ草で調子を取りながら、歌を歌って下手から登場)

『あれっ?』
(勘解由介を見つけて、袖幕に身を隠す)
(勘解由介を見つけて、袖幕に身を隠す)

『(おみつを認めて)これ、その者、出て参れ。私は、怪しい者ではないぞ。』
(おみつ、用心してチラチラ見ている)

『怪しいもんは、みんな、我がでは怪しぐねぇって 言うんだ。おとっつぁまがそう言ってたど。』

『(小さく笑って)はっ、はっ、はっ、そうか、賢いおとっつぁまだな。』

『(父親を褒められ、気分がよくなって)おんつぁま。』(近づく)

(心の中で「おんつぁま、せめてお兄ちゃんと言うて欲しいが・・・。」とつぶやく)

『おんつぁま、こごで何してただ?』

『実はな、信州信濃を追われ追われて・・・』(等々と身の上話をしようとするが)

『昼寝してただか?』

『昼寝? そのような呑気なものではない。つまり、信州を追われ追われて・・』

『なんだどって杖なんかついてんだ? おんつぁま、目ぇでもわりぃだか?』

『目は良く見える。そなたの可愛い顔も良く見えるぞ。』

『えへっ!(嬉しい)』

『実は、その・・・立っていられぬのだ。』

『な~してぇ? 足わりぃだか?』

『いや、足も悪くはない。ただ・・・。』

『ただ?』

『腹が・・・。』

『腹~? 腹いてぇだか? あっ、んだんだ。地蔵様さ あがってだお供え物、あのだんご食っただな。あれなあ、おらえのおっかさま、十日も前にあげただど。あんなだんご カラスも食わねぇ。おんつぁま、あれ食っただべ?』

『いや、そうではない。そなた、よくしゃべるな。』
(勘ケ由介、目が回ってクラクラと体が動く)

『なじょした?』

『なんの、これしき。腹が・・などとは言えぬ。武士の恥じゃ。』

『何 ゴニョゴニョくっちゃべってんだ? 言いでごどを言わねっでと、病気のもど。ほれ、おらが背中叩いてけっから(くれるから)、言いでごど 言わっしぇ!』

『あ~ これこれ、背中を叩かれて、その上 蹴られたんでは、どうにもたまらぬ。』

『何 かだってんだ。あんべぇわりぃ人、蹴っ飛ばしたりしねがら、言いでごど早ぐ言わっしぇ』

『しかし』

『しかしも、へちまもねぇって!』

『腹が・・・。』

『腹が なじょした?』(背中を叩きながら)

『腹が減っている!』

『んだのがぁ。』(笑い出す。勘ケ由介もつられて笑う)

『雨露をしのぐこと、三日も経とうか。腹が減って目が回る。』

『んだったのなぁ。 (何か考えていたが)おんつぁま、黙ってこごさ いらっしぇよ。おみつ、ちょっこら 家さ行ってくっがら。』

『おみつとやら、どうするのじゃ?』
(おみつ、キーンと走って行き、キーンとだんごを持ってくる)

『はいよ おんつぁま、おっかさまが寄ごした。』

『何? これを私にくれると言うのか?』

『うん、できたばっかしのじゅうねんだんごだど。早ぐ、食わっしぇ!』

『かたじけない。うれしいぞ。うまい。おみつ、本当にうまいぞ。』
(夢中で食べながら、勘ケ由介 流れる涙を抑えられない)

『んだ 『んだか? ほんだ良がったな~。』

『なあ おみつ、拙者 何か恩返しをしたい。』

『恩げえし? 』

『そう、何かそなたの役に立つことをしたい。』

『う~ん。(考えて)んだな~おら 読み書ぎでぎねがら、字が習いでぇな。』

『よし、字を教えることなら、拙者にもできるぞ。』

『んだら おんつぁま、おみつの家さ 行ぐべ。(振り返って)早ぐ こらっしぇ!』

『(ためらうが)うん 行ってみよう。』
(周りをぐるりと見回して)

『ここは、存外 良い所らしい。おみつ、ここは何と言う?』

『おら 知んにぇ。』

『拙者、この地を「葛尾」と呼びたい。郷里の葛尾のごとく豊かな地となるように、この地を「葛尾」と呼ぼう。きっと栄える地となるように 拙者は労を惜しまぬ。』

『か、づ、ら、お?』

『そうだ。気に入ったか?』

『うん、気に入った。』
(二人、笑いながら下手に退場)
(キジが二人を見送るように、上手から登場)

『こうして信州よりの落人、勘解由介は「葛尾」の住人となりました。勘解由介は、村人に学問を教え、やがて 藩侯に仕えるまでになりました。村は、少しずつ豊かな地となったのでございます。後に、勘解由介の子孫に当たる第4代好倉(よしくら)が商いを手広くして、松本三九郎と名のり、村人は三九郎一族を「葛尾大尽」と呼び称えたのでありました。これより、およそ二百年に及ぶ「葛尾大尽物語」の第一章でございました。』
第2章「四代目三九郎、聰通の頃」

『物語は、これより初代松本三九郎 好倉より、四代目三九郎 聰通の頃となります。初代三九郎が興した商いは その後、代を経て木材・塩・生糸そして鉄と広がり、葛尾大尽の名は、三春・相馬・棚倉を始め、遠くは京都・大阪まで知られることとなりました。四代目三九郎 聰通は、四十八の家屋敷を持ち、商才に長け人望厚く、村人からも尊敬されておりました。ですが、何か足りないものがある、心にポッカリと穴の開いたような寂しさ・・・。さて これは一体何なのだろう。思い巡らせてみますと、先頃 商いで訪れた京都のとある屋敷で見かけた美しい娘、イネへの恋心なのでございました。白百合のごとく清らかなその姿、鈴を振るような愛らしいその声を思うたびに、聰通の胸は ザワザワと波打つのでございました。』
(聰通、上手より登場)

『は~ (ため息)』

『いかがなさいました? お大尽さま。』

『手紙(ふみ)が来ないのだ。』

『手紙?』

『実は、イネ殿の親御に 私の思いを手紙にしたためた。』

『ほ~』

『イネ殿を、この地に迎えたい・・とな。』

『つまり・・・。』

『つまり、嫁に欲しいということだ。』

『して、返事は?』

『来ないから、眠れぬ夜を過ごしておる。』

『ならば、私めが、どこまで返事の手紙が来ているか、見定めて参りましょう。』

『おお そうか、すまぬがそうしてくれ。』

『しばし、待っていてくださいませ。』
(キジ、バタバタと飛んで行く)
(その間 聰通は、ウロウロと動き回っては、ため息をつく)
(キジ、手紙をたずさえて、戻って来る)

『おお~ すまぬ。』
(手紙を受け取り、開けて読もうとする)

『こ・こわい! 何と書いてあるのか、知るのが・・・恐ろしい。』

『お大尽さま、ご心配めされるな。なるようになる! で、ございますよ。』

『そうだな、では 読むぞ!』
(しばしの間)

『お~っ!』

『何と 書いてありました?』

『イネが嫁に来るぞ! なんと喜ばしいことだ! キジよ、お前に感謝するぞ。さっそく、嫁取りの支度だ!』
(聰通、軽やかに退場)

『こうして 聰通は、イネを迎えることとなりました。それから月日は流れて、三年目。聰通とイネは仲睦まじく、人もうらやむ夫婦となったのでございます。ところが・・・。』
(キジ、退場)
(聰通、その後ろからイネ登場)

『どうしたのだ イネ、顔色がすぐれぬが・・・。』

『大丈夫でございます、だんな様。』

『しかし、下男どもが言うておったぞ。「おイネ様は、まるでかぐや姫のよう。月を見上げては、時々泣いておられる。」とな。何か悩みがあるのなら、何なりと話してみよ。』

『だんな様 お気を悪くせずに、聞いてくださいますか?』

『もちろんだ。』

『イネが、この地に嫁いで三年が経ちました。お優しいだんな様、何不自由のない暮らし。イネは本当に幸せ者でございます。この上の望みなど、バチが当たりそうで・・。(うつむく)』

『遠慮することは ない。お前と私は、夫婦ではないか。お前の寂しい顔など見たくはない。いつも白百合のように微笑んでくれるお前が、私は好きなのだ。さあ 話しておくれ。』

『はい。誰にでも忘れられない風景というものがございます。私は比叡山や大文字山など、京の山々を見て育ちました。ことに桜の頃は美しく、私は京の都に生まれたことを本当に嬉しく思っておりました。長じてからは、父の商いのお供をして、近江にも度々出かけました。その折に見た、近江八景も忘れられない風景の一つでございます。ここ、葛尾に来たことを悔やんではおりませんが、時々京の都のたたずまいが 無性に恋しくなります。京の山々に陽が昇り、陽が落ちる。時と共にうつろう その風情が懐かしくて・・・ 夜ともなると、たまらない気持ちになるのでございます。』

『そうか・・・。お前は、それほどまでに都を愛しておるのか・・・。知らなかった。』
(しばらく考えて)

『それならば、ここに都を作ろうではないか。』
(イネ、聰通の言葉を、わかりかねて)

『はい? だんな様、それは、どういうことでございますか?』

『イネ、半年待つが良い。半年の後には、ここ葛尾にお前の好きな風景を作ってやろう。そうすれば もうお前は泣かずともすむ。』

『そんなことが出来るのでしょうか?』

聰通 『できるとも! やってみせるとも!』
(二人、退場)
(キジ、スッと舞い降りて)

『それから半年後、聰通の屋敷には なんと近江八景を模した、大層立派な庭園が造られたのでございます。イネがこよなく愛した桜も、京都から運ばれました。春には、美しい花を咲かせた桜の木を、イネは どんな想いで見つめたのでしょう・・・。』
(聰通・イネ、登場)
(妻に、庭を見せて)

『イネ、どうだ?』

『まあ・・・。(しばし、絶句)だんな様、私が小さい頃から見た風景、そして桜の花は、まさしくこの姿でございます。イネは、イネは・・・何という幸せ者でしょう。(泣く)』

『そうか。なあ イネ、私はここに能舞台を作ろうと思う。都から、能や狂言を呼び寄せよう。そうだ、大文字焼きに見立てて、向かいの蟹山で 野焼きもやろう。お前の雅びな心が枯れぬよう、お前が愛した風情や文化を、私も愛そう。夫婦とは、そういうものではないのか?』

『はい。イネも、ここ葛尾の良さを、この身に染み込ませましょう。誰よりも、だんな様のために・・・。』
(二人、見つめ合う)

『聰通が、愛しい妻イネのために取り入れた、庭園や能・狂言などは、奥州の地 葛尾に洗練された、あでやかな文化を育てることとなりました。そして、遠く 京都から運ばれた桜は、「京桜」と呼ばれ 村人に親しまれることとなりました。聰通が植えた桜は、昭和の時代まで花を咲かせ、その後枯れてしまいましたが、現在でも大尽屋敷跡の近くには、その子孫と言われる桜が見られるそうでございます。それは、図らずも聰通とイネの夫婦愛の結実 とも言えるのではないでしょうか?さて、これより時は更にくだり、七代目三九郎 兼通の頃へと、物語は進むのでございます。』
第3章「七代目三九郎、兼通の頃」
(奥に、大尽屋敷。手前に田畑、作物は枯れている図)

『七代目の三九郎 兼通は、若き頃より書を好み、短歌・俳句を作り、琵琶を奏でる風流人でございました。少々、体が弱かったこともあり、家屋敷から出ることも少なく暮らしていたのでございます。「飢饉」と聞いても、兼通にとっては、外の世界の出来事。「米がないなら、麦を食えば良い。麦が取れぬならば、豆があるではないか。」と、村人の窮乏には、トンと関心のない様子でございました。しかし、いわゆる天保の大飢饉の年、世情に疎い兼通も、すさまじい飢饉のありさまを、知ることとなりました。』
(兼通、屋敷の前で独り言)

『秋ともなれば、田畑の収穫も終わり、村人の家々からは、夕げの支度をする煙がたなびくものだ。わしは、屋敷からその様を眺めるのが好きなのだ。錦織りなす秋の里山、あちこちに上がる白い煙。それはまこと平穏な村の姿。それがどうだ。今年は、一筋の煙も見えぬ。そうして、人々の嘆き悲しむ声が、わしの屋敷にも日毎・夜毎聞こえてくる・・・。薄気味の悪いことだ。一体、何が起きているというのだ?』

(弱々しく泣きながら、下手より登場)

『これ ぼうず、どうしたのだ? なぜ 泣いておる?』

『おっかさまが・・・。』

『おっかさまが、どうした?』

『死んじまっただ。』

『何? おっかさまが死んだ? なぜだ?』

(けさ松は、静かに泣くばかり)

『病気か?』

(首を横に振る)

『怪我をしたのか?』

(首を横に振る)

『もしや、誰かに殺められたか?』

『食いもん、あれぎり 持っていがっちゃ・・・。』

『ん? 誰かが、お前とおっかさまの食べ物を奪ったと、言うのか?』

(うなずく)

『そんなむごいことをしたのは、誰だ?』

『地主さまと、お大尽さま・・・。』

『何?(絶句する)わしは、こんな いたいけな子供を飢えさせた覚えはないぞ。嘘だ、そんなはずは・・・そんなはずは、ない。お前達村人の食いぶちは残しているはず・・・。』

けさ松 『いつもの年だら、んだべげんとも、今年は凶作で飢饉で、米も麦も、草まで枯れっちまった。年貢、取立てで、あれぎり持ってがっちぇ、跡さ、なんにも残ってねぇ。おとっつぁまは、死んだ。あんにゃも、あんねも・・・。さよだけが残って・・・。』

『さよ? さよとは、お前の妹か?』

『(うなずく)おら、お大尽さまに頼みさ行ぐべと思って 出がげで来ただ。おらなんか・・・おらなんか どうなったっで、かまねぇ。んでも、さよを・・・さよだげでも 何とか助けでくんちぇって、頼みさ 行ぐだ。』

『こんな幼い身で、妹を助けたい一心で来たというのか・・・。何としたことだ。村に煙が上がらなかったのは、夕げの支度ができなかったからか・・・。あの声は、父や母が我が子を亡くした、嘆きの声か・・・。』
(兼通、ハッと思い当たって)

『そうだ! その昔、我がご先祖は、信州からたどり着いたこの地で、娘から貰ったじゅうねんだんごに、命を救われたと聞いたことが・・・。』
(フラフラとよろめくけさ松を、兼通が抱き止める)

『どうした? しっかりせい。』

『おらも は~、もうじき三途の川さ 行ぐ。おとっつぁまや、おっかさまにも、すぐに、いっきゃえる・・・。』

『馬鹿を言うでないぞ! わしが、そうはさせぬ。ぼうず、名は 何という?』

『けさ松。』

『けさ松よ。わしは、何という愚か者だったか。我が蔵を満たしても、村人の胃の腑を満たすことをしなければ、いずれ 我が身も滅ぶというものを・・・。けさ松、待てよ。お前と妹に、いや、村人全てにうまい飯を食わせてやるぞ。米がなくなったら、ヒエや粟や じゅうねんのだんごを作れば良い。美味いだんごを、一緒に食おうぞ。なあ、けさ松。』
(けさ松、答えず)

兼通 『けさ松、けさ松、どうした。死ぬでないぞ。ほらほら、わしの背に・・・。』
(兼通、けさ松を背負って)

『お前達を必ず、助けてやる!けさ松、お前に会わなんだら、七代目三九郎は、危うく、恩知らずの三九郎となるところだった。』

『(切れ切れに)ぬぐいな~・・・。この背中、あったげぇな~。』

『(涙が、込み上げてくる)幼子の心も知らず、何が風流だ? わしの今までしてきたことの、何と空ろなことか・・・。けさ松、わしは、これからお前達と一緒に、本当の人生を生きるのだ。』
(けさ松を背負い、兼通上手に退場)
(キジ、上手より登場)

『七代目三九郎 兼通は、この後、屋敷の蔵という蔵から 惜しみなく米を村人に与え、米が尽きれば、ヒエ・粟・じゅうねんでだんごを作り、村人に分け与えたそうでございます。兼通は、これよりほどなくして、病に倒れました。しかし、兼通のそばには、ひたむきに世話をする けさ松の姿があったそうでございます。』
ケ~ン(舞台を一回り、飛び回って)

二百余年に渡って、葛尾村に繁栄をもたらした葛尾大尽・松本三九郎一族は、その後(のち)、二度の大火に見舞われ、一族はこの地を離れ、今や、イネが寄進した大日如来像や、屋敷跡が残るばかりとなりました。しかし、今も残る葛尾大尽の物語は、春に桜が咲くごとく、秋に紅葉が色づくごとく、葛尾の人々にいつまでも語り継がれてゆくことでしょう。葛尾大尽物語は、「三匹獅子舞」のうちに、幕とあいなりまする。
(「三匹獅子舞」が、子ども達によって舞われ、人形がそれぞれ登場し、最後にキジが「終」の布を下げて)